急行荷物列車をつくってみよう。(その6)マニ44のテールライトを光らせる・前編。
2009年11月22日 21時49分  月齢:5.7[六日月] 潮汐:中潮
月齢:5.7[六日月] 潮汐:中潮
(最終更新日:2009年11月24日)
16年前に投稿 | 鉄道模型 | 2件のコメント
2分ぐらいで読めます。
この記事は情報が古い場合があります。
さて、独特の妻面を持つマニ44を最後尾に組成したときに映えるように、テールライトを点灯させてみることにしました。
φ0.7mmの穴を開けたところ、ボリュームがなかったので、φ1.0mmに拡げました。点灯方式は当初LED+抵抗を考えていたのですが、いろいろと調べてみると定電流ダイオードというものがあるらしい。制御電圧を変化させても明るさが変わらないとのことなので、早速採用してみます。今まで経験がない技法なので、「ヘッドライト/テールライトの白色・電球色LED化」を大いに参考にさせていただきました。以前模型をやっていた頃(20年以上前)は麦球しかなかったなぁ。
電子部品を購入。LEDはφ3.0mmのいちばん安いもの。定電流ダイオード(CRD)はE-153(15mA)とE-103(10mA)を購入してみます。整流ダイオードは1S1588の互換品です。LEDもダイオードなのだから、整流ダイオード無しでも逆方向には電流通さないのでは、と考えたりもしたのですが、よくよく考えるとLEDの耐電圧はせいぜい5Vなので、やっぱり整流ダイオードは必須なんですね。
いくら車内からLEDで照らすといっても、穴をあけただけでは寂しいので、レンズをはめてやります。単純に透明の物質で穴をふさぐのが目的なので、高価なパーツは意味なし。透明スチロール樹脂φ2.0mmを火であぶってムニョーンとのばし、ちょうど1.0mmになった部分を使うことにします。
CRD→LED→ダイオードと回路を組んで、実験してみました。確かに印加電圧が低いときから全開まで、一定した明るさでLEDが点灯しています。当然極性が逆になると点灯しません。んー理想的な回路だなぁ。
LEDを並列にしてみました。ほんの少し暗くなりましたがほとんど差はないです。
伸ばした樹脂パーツで導光のテスト。これもまぁ、問題ないです。今回は樹脂で導光はあまり考えていないですけど。
伸ばした樹脂の中から、径がちょうどいい部分を2.0mm程度の長さに切り出し、レンズにします。特にクリアレッド等で塗装はしません。
このままでは車掌室全体が淫靡なムードで赤くなってしまうので、遮光板を設置します。こういうことは組み立てる前に考えておくべきですネ。完全に組んでからの室内に現物あわせで寸法を出してパネルを設置することは、かなり大変でした。あとはさらに隙間をプラ板やパテで埋めて完全に遮蔽する予定です。むー、せめて内側は淡緑にでも塗装しておくべきだったか。あんまり気にしてないですケド。
次は回路部分を構成していきます。
古い記事・新しい記事
- 古い記事 [2009年11月20日]
- ← 急行荷物列車をつくってみよう。(その5)マニ44の床下と台車
- 新しい記事 [2009年11月30日]
- → 急行荷物列車をつくってみよう。(その7)マニ44のテールライトを光らせる・中編。







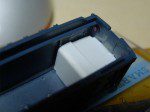
[...] by admin on 11月.24, 2009, under 未分類 さて、独特の妻面を持つマニ44を最後尾に組成したときに映えるように、テールライトを点灯させてみることにしました。φ0.7mmの穴を開けたところ、ボリュームがなかったので、φ1.0mmに拡げました。点灯方この記事の続き [...]
[...] 後尾に組成したときに映えるように、テールライトを点灯させてみることにしました。φ0.7mmの穴を開けたところ、ボリュームがなかったので、φ1.0mmに拡げました。点灯方この記事の続き [...]