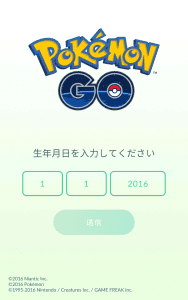TOMIX DD51-592(ユーロライナー色)をいろいろといじる。
2016年08月12日 18時00分  月齢:9.6[十日月] 潮汐:長潮
月齢:9.6[十日月] 潮汐:長潮
9年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません
2分ぐらいで読めます。
亀師匠から、TOMIX DD51-592(ユーロライナー専用色)をいただきました。これで客車と機関車ともにユーロ色でそろえて走らせることができます。
が、その前に。いただいたDD51は、TNカプラーとアーノルトカプラを前後につけているので、KATOカプラー換装済みの客車とはカプラーを交換しないと連結することができません。
カプラー交換の方法はここに書かなくてもいいくらい、いくらでも紹介されています。いまさらここで詳しく述べるのもアレなので、他のサイトを見てくださいね。
かもめナックルカプラーをブラケットにおさめて、はいできあがり。(実はカプラーがばらけないようにピンを固定したり、カプラー後端のコの字部分上部を斜めに削ったり、少しの細工は必要なのです。)
少し高さがずれているようですが、どちらかというと客車側が低いようで、他の客車だとピッタリ合いました。
これで無事に組成できたのですが、せっかくなので付属のオプションパーツをすべてくっつけることにしました。まずはヘッドマーク。ボンドGクリヤーを少し付けてチェーン部分につけてやります。うんこれはなかなかかっこいいぞ。
アンテナも屋根をカッターナイフでコリコリと加工して取り付けました。ちょっとゴチャゴチャ感が増して、男らしく。
このように完成。信号炎管はカバー付きのほうを取り付けてみたけれど、これで合っているのかなぁ。まあ雰囲気は出ているので合格ですー。