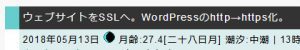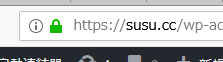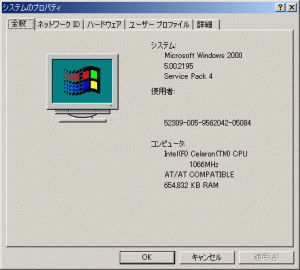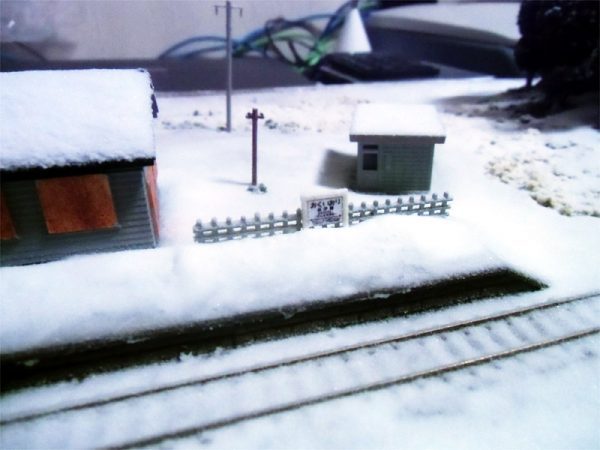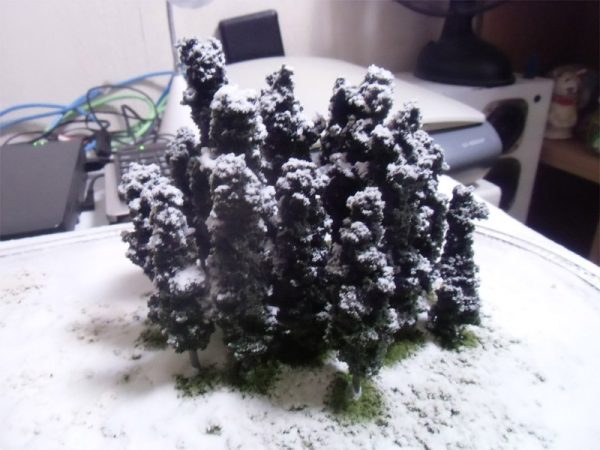「仮想通貨(暗号通貨)」カテゴリーを作りましたー。
2018年05月15日 21時00分  月齢:29.4[月隠] 潮汐:大潮
月齢:29.4[月隠] 潮汐:大潮
8年前に投稿 | 暗号資産(仮想通貨) | コメントはありません
3分ぐらいで読めます。
仮想通貨の世界に足を突っ込んで10か月目。ホントはもっと早く2017年のうちに発信したかったんですけど、まぁいろいろありましてようやく今日というわけです。暗号通貨のほうが正しい気がするけれど、日本じゃ仮想通貨のほうが通りがいいので、SEOの観点からも仮想通貨という表現をを多用することにしますね。
ビットコインに興味を持ったきっかけ
「仮想通貨」「ビットコイン」という言葉は聞いたことがあったけれど、それもマウントゴックスの事件で聞いたことがあるくらいで、なんていうか、触れてはいけない世界のような気がしていました。ところがある人のある一言がきっかけで、とんでもなく興味を持ってしまったのです。
2017年8月、ボロいけど実用的だったヴォクシーのラジエターがパンクしてオーバーヒートしました。エンジンや補機を修理するとかなりのお金がいるし、ボディーは傷だらけだし、買い替えようかということで前回もお世話になった営業担当のS氏に連絡。さっそくいくつかの車を見せてくれることになりました。ヴォクシーはディーラーにドナドナされて置きっぱなしのため、S氏が家まで来てくれました。で、展示場までの道程で聞いた言葉にびっくり。
「友達がビットコインで70億円儲けたけど、一気に引き出せないので毎日50万円ずつ下ろしてる。」
はあ?! 今まで「パチスロだけで生計を立てている」「競馬のオッズ解析で年数千万円稼いでいる」という凄ワザの人は知っているけれど、桁がちがう。だいたいこれが本当の話かどうかもわからないけれど、でもあながち嘘とも思えない。
そこで、ビットコインについていろいろ調べてみることにしました。もちろんビットコイン以外にもいろんな通貨がたくさんあるなんて、想像すらしていませんでした。
一攫千金も夢があるけれど、技術的な魅力がたまらない!
たしかに最初に心を揺さぶられた理由は一攫千金の可能性があることなのですが、調べれば調べるほど、ブロックチェーンの仕組みが良くできていること、法整備が追いついておらず市場原理で価格が大きく変動すること、機能が次々と追加されることなど、技術的にとてもおもしろい。
とにかくこの世界に飛び込んでみたくて、まずは「Coincheck(コインチェック)」、つぎに「bitFlyer(ビットフライヤー)」、それから「Zaif(ザイフ)」と、次々とアカウントを作っていきました。
ジェットコースターのようなチャートがたまらない!
2017年8月から始めたのですが、最初に思ったことは「あと1年、いやあと半年でも早く知っていればなぁ」ということ。とはいうものの、秋から冬にかけての価格推移は嬉しかったですね。自分は何もしていないのに日に日に価格が上がっていく(9月や11月に暴落もしたけど)。実体験としてこの感覚を最初に味わったのはモナコイン。12月にはいろんな通貨で体験しました。
資産は、なかなかたまらない…
12月までは楽勝と思っていたのですが、その後、まあいろいろあったわけで、今のところ投資金額を下回っています。けど、明日さえどうなるかわからないのが仮想通貨の魅力。タンス貯金や銀行預金、競馬やパチンコよりも、自分の判断で資産を増やすことができる仕組みなのです。
というわけで作った新カテゴリー。新たに仮想通貨だけのブログを作ったほうがいいかなとも思ったのですが、当分はこのサイトでやっていくことにしますね。