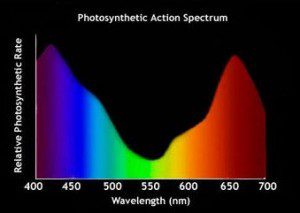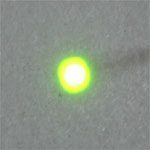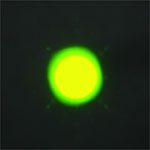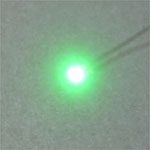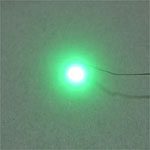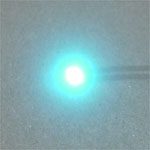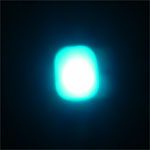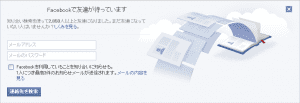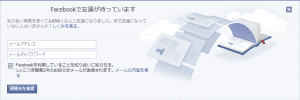無線か有線か? 家庭内LANの更新。
2013年01月18日 18時00分  月齢:6.7[七日月] 潮汐:小潮
月齢:6.7[七日月] 潮汐:小潮
(最終更新日:2019年09月02日)
13年前に投稿 | ウェブ・IT関係 | コメントはありません
2分ぐらいで読めます。
実は、2012年末から2013年初にかけて、自宅の無線LANアクセスポイントが壊れてしまい、自室のパソコンからネットワークにつながらなくなりました。ルーターやNAS、ドメインコントローラーは有線で接続しているので問題はないのですが、ユミコちゃんのパソコンも伊織のパソコンも無線LAN(IEEE802.11b)でつないでいたのでとにかく不便で…
壊れたのは、corega WLAP-11 V2。昨年の秋頃からたまに再起動しないと接続が切れることがあったのですが、とうとう有線LANのランプも点灯しなくなりpingさえ飛ばなくなってしまったのです。ケースの裏は少し膨らんで、薄茶色に焦げたような感じになっていました。これとまったく同じ製品をもう1つ持っていて(もらい物)、使えるかどうか接続してみたところ、同様に有線LANにもつながりません。相当古い製品であることは確かですが、同じ症状でつながらないなんて、S○NYタイマーみたいなものでも入っているのでしょうかねぇ。
もう1つ、ジャンクなアクセスポイントを持っていて、引っ張り出して接続してみました。
BUFFALO WLM2-A54G54。これは有線LANにも正しくつながって、無線LANのランプも点くし、一見使えそう。でも、全然電波が飛びませんでした…
もうこれを機会に全部の部屋にLANケーブルを張り巡らそうかな。スピードも出るし。なんて考えたものの、あちこちの部屋にケーブルを張るのはやっぱり大変。今回も有線化はあきらめて無線にしとこ。
探してみると、以前よりもずっと安く買えることがわかりました。PLANEX MZK-MF300Nに決定。
今まで11Mbpsだけだった無線LAN環境が、2台は54Mbpsでつながるようになりましたー。300Mbpsはまだ試していないなのです。いつ使おうかな。